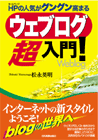「思考」と一致するもの
@(アットマーク)の歴史と呼び名
「@(日本ではアットマーク)」という記号についての起源について、少し調べてみた結果をまとめておく。アットマークというのは日本だけの呼称で、世界的にはまるで通用しないようだ。その歴史(そもそもの発端――中世と、電子メールでの使用)ならびに呼び方について、ロバート・フルフォード氏のコラムに詳しく書かれていたので、訳してみた。
※この記事は2004年のものです。最新の情報はアットマーク - 閾ペディアことのはを参照ください。
愛国心(または国という枠組みへの帰属感)反応集
自分で作るのもどうかと思いますが。
コメント欄ではいろいろ関係ない話が展開されていますが、それは置いておいて、他のサイトやブログでのコメントから非常に興味深いものをまとめておきます。
「愛国」問題を出すとこのように誤読される
※この記事は草稿としてボツにしました。Gypsy Blood「愛すべき場所は二つ」/松永的愛国心論まとめ編にて改稿しています。
やはり恐れていたとおりになった。前の記事「偽りの「愛国」、隣国への嫌悪」で愛国心の表し方についての疑義を示した。そして、内容も読まずに私が「反日」であるとか、「朝日的」とか言い出す人が絶対出てくることが予測されたのだが、案の定そのとおりだった。だから、いやだったのである。
しかし、私が「中国の反日教育」に対しても批判しているのが読み取れないほど難解な文章だったのだろうか、と、自らも反省中。
そこで、コメントの中にいくつか有意義な話題もあったので、改めて記事としてまとめてみたいと思う。
なお、途中までしか読まずにコメントを付けるのは勝手だが、当方もそういうコメントには対応しないのでご了承を(そういうコメントには見当外れなことしか書いてないし)。
縦書きアタマと横書きアタマ
ブログ本が2冊、しかも縦書きで出ている。
- 松永英明『ウェブログ超入門!』日本実業出版社¥1470
- 長野弘子・増田真樹共著『1日5分の口コミプロモーションブログ』英治出版¥1575
この2冊はどちらも「ブログの設置の方法」よりも「運用の仕方」に重点を置いているのが特徴。拙著『ウェブログ超入門!』の方は、とにかく初心者向けに、トラックバックのマナーとか考え方とか、どういう記事をどういう風に書いたらいいかとか、引用の決まりとか、あとはメディアとの関係とか、知識経済ヴァージョン2とか、クリエイティブ・コモンズとかに触れている。
一方、長野さん、maskinさんの『1日5分の口コミプロモーションブログ』は、内容はかなり似ているのだが、もう少しIT関係者向けの印象が強い。活用法について書いた部分では、ビジネスでどう使うかという方向を向いている。ネット中級以上の人向け、あるいは、会社でブログについてプロモーションするときの資料として使えるのではないかと思う。
さて、この縦書きについて「ブログ神」こと平田さんがコメントを書かれている。今回はこのことについて書いてみたい。
切り捨てられるアジア音楽ファン【音楽関係者にまで裏切られた!?】
「私たち音楽関係者は、著作権法改定による輸入CD規制に反対します」に「声明文」が出されている。もちろん、「輸入CD規制に反対」という趣旨には賛同している。しかし、その内容については、絶対に
アジア盤の邦楽CDの逆輸入防止を目的とするならば、それを法案に明文化することを求めます。
つまり、この「音楽関係者」は「アジア盤は禁止されてもいい」というのだ。
しかし、それはアジア音楽ファンに対する裏切りであり、ものごとを大局的に見ていない声明である。
●5月15日追記。無用な混乱を招いたことをお詫びし、一部訂正等を加えた上で末尾に追記します。
「思考」が運命を変える
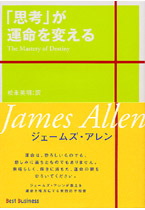 「思考」が運命を変える
ジェームズ・アレン著/松永英明訳
「思考」が運命を変える
ジェームズ・アレン著/松永英明訳
ワニブックス(文庫)で発売中です。コンビニでも売ってます!税込500円。
今回の本は実践的な内容になっています。また、気楽に読めると思います。
・ジェームズ・アレン・ネット
木村剛氏は「アフィリエイト」をわかっていない――ブログに向かないシステム
もう2週間ほど前の記事ではあるが、週刊!木村剛: 「週刊!木村剛」にトラックバックして、アフィリエイトでおカネ儲けしよう![ゴーログ]という記事がある。私は木村剛氏をブログでしか知らないのだが、「金融・企業財務に関する総合コンサルティング」「経済同友会企業会計委員会委員長」といったプロフィールからすると、経済のプロのようである。
しかし、この記事を読む限り、木村剛氏はアフィリエイト・プログラムがどういうものか、まったく理解していないようなのである。
『「意志」と「人生」の法則』は今までのジェームズ・アレン本と何が違うか
今回訳した『「意志」と「人生」の法則』は、今までのジェームズ・アレン本(例えば代表的な『「原因」と「結果」の法則』など)と少し違うところがあります。この本はジェームズ・アレンの晩年の本であり、それ以前の本よりも非常に広い範囲のことがらを扱っています。
有名な初期の代表作 "As A Man Thinketh" から受け継がれた思想、つまり「人の思考がその人の人生をよくも悪くも決めていく」という考え方は変わりません。それはアレンの土台となる思想でしょう。
しかし、それだけではなく、たとえば「戦争と平和」――なぜ戦争が終わらないのか、あるいは思想・宗教の対立はなぜ尽きることがないのか、といった問題についても明確に示しています。これは現代にも通じる、というより、今こそ必要とされている視点かもしれません。
例えば、戦争に反対することそのものが戦争を生み出しているとしたら――?
今回訳していて、ジェームズ・アレンというのは硬派だとつくづく思いましたね。アレンは決して我々を甘やかしてはくれない。単に癒してくれるだけの思想などではなく、むしろ我々を突き放すところもあります。単に「レッツビギンや!ポジティブやで!」と叫んでいるわけでもなく、「こうすれば楽々儲かるよ」とも絶対に言ってくれない。そこにアレンの面白みがあると思います。その硬派的な雰囲気を出すために、訳語もかなり検討しました。
というような話はこれから「ジェームズ・アレン・ネット」の方でじっくり書き込んでいきたいと思います。どうぞよろしく。
ゴーストライターとは何者か
「あの人の本は、ゴーストライターを使ったんだって」
こういうと、たいていはその著者を貶めるような雰囲気が出てくる。「あの人は偉そうなこと書いてるけど、実際に書いたのは別の奴なんだぜ」というふうに。
だが、ゴーストライターを使ったからといって、その本の価値が必ずしも下がるわけじゃないのだ。もちろん、非難されても仕方ないゴースト本もあるかもしれない。だが、少なくとも自分が請け負ってきたゴーストはまったく違うのである。
私は過去に数年間、ゴーストライターとして飯を食っていたことがある。ゴーストライターという「仕事」の実際について、少し説明してみたい。
「ウォッチャー」の権利など守る必要はない。儀礼的無関心2
以前「こっそりやっているサイトには、あえてリンクしないという配慮も必要ではないか」という話題が一部で取り上げられ、そのキーワードとして「儀礼的無関心」という言葉が使われるなど、いろいろ考えるところがあった。このサイト内でも「ネットでの儀礼的無関心」かコミュニケーション優先かという記事を公開した。
しかし、ARTIFACT -人工事実- 2004/01/31「ネット教習所をシステムとして作る-儀礼的無関心について-」を読んで、自分自身がその話題の発端を間違って受け取っていたことに気づいた。
アクセスが集中した小規模サイトが焦って記事を削除したり、サイトを閉鎖したりすることがある。そんなことがないように思いやりを持って、あえてリンクしないであげようよ……という趣旨だとてっきり思いこんでいたのだが、何のことはない、最初に言いだした人は「こっそり見る権利(チラ見)を失わせるな、と言ってる」のだった。要は覗き見である。その出歯亀行為を「公共の利益」にすり替えて議論が進められていた。このあたりを完全に見落としていたのは、私の大きなミスだ。
そこではっきり言わせていただく。「覗き見の権利など、守る必要は一切ない
覗き見する先がなくなったからと言って文句を垂れるのは筋違いだし、ウォッチャーとしても恥ずかしい態度である。ウォッチ対象が潰れたら黙って次の対象を探すウォッチャーには何も言わないが、外からバカにして見ていただけの人が「せっかく俺が見ていたのに」と文句を言うのはおかしくありませんか?そして、それこそバカにされ続ける人の尊厳を損なう行為ではありませんか?